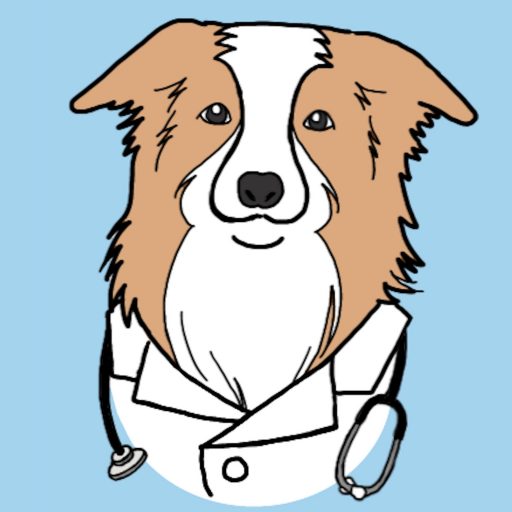愛犬の水を飲む量が多い!多飲するので病院に連れて行ったけど、
- 原因がわからないと言われた...
- 様子、経過を見てくださいと言われたけど心配...
- 検査してくれなかった...
- 病院ではよくわからなかった...
- 病院では質問しづらかった...
- 混乱してうまく理解できなかった...
- もっと詳しく知りたい!
- 家ではどういったことに気をつけたらいいの?
- 治療しているけど治らない
という事でこの記事に辿りついたのではないでしょうか?
ネット上にも様々な情報が溢れていますが、そのほとんどが科学的根拠やエビデンス、論文の裏付けが乏しかったり、情報が古かったりします。
中には無駄に不安を煽るような内容も多く含まれます。
ネット記事の内容を鵜呑みにするのではなく、
情報のソースや科学的根拠はあるか?記事を書いている人は信用できるか?など、
その情報が正しいかどうか、信用するに値するかどうか判断することが大切です。
例えば...
- 人に移るの?
- 治る病気なの?
- 危ない状態なのか?
- 治療してしっかり治る?
これを読んでいるあなたもこんな悩みを持っているのでは?
結論から言うと、食物の内容にもよりますが、一般的に1日水分摂取量は約40~60mL/kg/日(体重0.75×70)とされています。
しかし渇感が増大し、正常な摂水量を超える量(犬では1日当たり90mL/kg以上、猫では1日当たり45mL/kg以上)の水分摂取が認められる状態のことを多飲・多渇といいます。
この記事では、愛犬の水を飲む量が多い!多飲する場合について、その理由をアカデミックな面からまとめました。
この記事を読めば、愛犬の水を飲む量が多い!多飲する際の症状、原因、治療法までがわかります。
限りなく網羅的にまとめましたので、ご自宅の愛犬の水を飲む量が多い!多飲するところを見つけた飼い主は、是非ご覧ください。
✔︎本記事の信憑性
この記事を書いている私は、大学病院、専門病院、一般病院での勤務経験があり、
論文発表や学会での表彰経験もあります。
今は海外で獣医の勉強をしながら、ボーダーコリー2頭と生活をしています。
臨床獣医師、研究者、犬の飼い主という3つの観点から科学的根拠に基づく正しい情報を発信中!
記事の信頼性担保につながりますので、じっくりご覧いただけますと幸いですm(_ _)m
» 参考:管理人の獣医師のプロフィール【出身大学〜現在、受賞歴など】
✔︎本記事の内容
獣医師解説!犬の多飲!水飲む量が多い時〜原因、症状、治療法〜
この記事の目次
犬の多飲、水をよく飲む量はどれくらい?

食物の内容にもよりますが、一般的に1日水分摂取量は約40~60mL/kg/日(体重0.75×70)とされています。
しかし渇感が増大し、正常な摂水量を超える量(犬では1日当たり90mL/kg以上、猫では1日当たり45mL/kg以上)の水分摂取が認められる状態のことを多飲・多渇といいます。
多飲には原発性多飲と代償性多飲があり、
原発性多飲は腎臓からの過度の水分喪失に対する代償機構としては説明できない飲水量の増加であり、
代償性多飲は様々な理由で腎濃縮機構が障害され多尿となり代償機構として飲水量が増加することです。

犬の多飲、水をよく飲む病気の分類と問題点

◎分類
原発性多飲と代償性多飲、もしくは両方の併発に分類され、多くは代償性多飲(特に後天性腎性尿崩症)です。
◎問題点
多飲は多くの飼い主が気づく重要な臨床徴候の一種ですが、多渇状態にある動物は水飲み場以外の場所でも飲水をしていることがあり、多飲の正確な評価は数日間の全飲水量と尿量を測定する必要があります。
しかしながら、屋外・屋内飼育の場合、飲水量・尿量の把握は難しく、飼い主は多飲に気づかなかったり、屋内飼育であっても多頭飼育や水道水から直接飲水する場合は飲水量の把握は困難です。
外観的に原発性多飲と代償性多飲を区別するのは不可能であり、鑑別のための検査が必要となります。
多飲が認められた場合、それが生理的変化なのか、病的変化なのか診断するために飼い主からの詳細な病歴聴取と、入念な身体検査が必要です。
生理的な飲水量の変化には食物の変更(ウエットフードからドライフードへの変更、高ナトリウム食、低蛋白食)や環境の変化(高気温、低湿度)などが挙げられます。
犬の多飲、水をよく飲む病気の病理発生

尿の生成および摂水量(渇き)は、主に腎臓・下垂体および視床下部の相互作用によって調節されています。
心房および大動脈にある圧調節装置も渇きおよび尿の生成に関与しています。
多尿は、視床下部で合成され、下垂体後葉で放出される抗利尿ホルモン(ADH)の分泌量が制限された場合や、腎臓が正常にADHに反応できなくなった場合に起こります。
多飲は、視床下部前方にある渇中枢が刺激された場合に起こります。
ほとんどの症例の場合、多飲は多尿の代償性反応として水分保持のために起こります(代償性多飲)。
このような症例の血漿は、相対的に高張液となる傾向があり、血液の高張化は渇機構を促進する。
代償性多飲は
- ADHの合成または分泌の減少や欠乏による中枢性(神経性)尿崩症
- 尿細管のADHに対する反応性の欠如による先天性(一次性)あるいは後天性(二次性)尿崩症
- 慢性の多飲多尿を引き起こす様々な原因
により腎髄質の溶質(特にナトリウムおよび尿素)が喪失することにより多尿になることで起こる。
また、ADHの分泌や腎尿細管での反応に影響を与える薬物による場合もあります。
稀に、多飲が起こり、その代償性反応として多尿が起こる場合がある(原発性多飲)。
このような症例の場合、その血液は過剰な摂水のために相対的に低張となり、ADH分泌が減少し多尿となります。
原発性多飲は心因性、消化器系疾患、視床下部渇中枢刺激、消化器浸透圧受容器刺激などにより起こります。
◎原発性多飲
・自律神経機能低下
▶心因性多渇(運動不足、ストレス環境下、疼痛、副腎皮質機能亢進症、甲状腺機能亢進症、肝性脳症)
・腎臓排泄以外での循環血液量の減少
▶消化器系疾患(下痢、嘔吐) ▶発熱 ▶過換気 ▶出血 ▶心不全
・視床下部渇中枢刺激
▶腫瘍 ▶外傷 ▶炎症
・消化器浸透圧受容器刺激
▶食物(高ナトリウム食)
◎代償性多飲
・ADHの合成または分泌の減少や欠乏
▶中枢性尿崩症(特発性、外傷性、腫瘍、下垂体の発達異常、嚢胞、炎症)
▶薬物(グルココルチコイド、アルコール)
・尿細管のADHに対する反応性の欠如
▶先天性腎性尿崩症
▶後天性腎性尿崩症
(副腎皮質機能亢進症〈クッシング症候群〉、子宮蓄膿症、糖尿病、慢性腎不全、初期の急性腎不全〈閉塞後利尿〉、腎盂腎炎、高カルシウム血症、肝機能不全、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能低下症〈アジソン症〉)
▶薬物(バルビツール、テトラサイクリン、ビンカアルカロイド)
▶腎髄質の溶質の減少(慢性多飲多尿の原因疾患による二次的変化、薬物〈利尿薬〉、輸液、低蛋白食〈尿素〉)
犬の多飲、水をよく飲む病気の対症療法

◎原発性多飲
水分摂取量を調節しつつ、素因となっている環境因子の排除
◎代償性多飲
点滴による脱水管理
犬の多飲、水をよく飲む病気の診断の進め方

問診、身体検査、血液検査、尿検査や画像診断を用いて中枢性尿崩症、先天性腎性尿崩症および原発性多飲(心因性多渇)以外の原因を除外できたときのみ改良水制限試験を注意深く行い、上記3疾患の鑑別を行います。
この上記3疾患以外の疾患に該当し、その疾患を治療して良好に制御しても多尿・多飲が継続する場合は3疾患のうちいずれかを併発している可能性を考慮します。
◎問診
- 動物の特徴(動物種、品種、性別)
- 病歴(薬物投与歴、摂食歴)
- 飼育環境
- 元気(異常興奮、鎮静、衰弱)
- 食欲(多食、減衰、廃絶)
- 体重(急激な削痩、腹部膨満に伴う体重増加、肥満)
- 疼痛の有無
- 皮膚性状(左右対称性脱毛、被毛の脱毛、発赤、発疹、痒覚、柔軟性、色素沈着、肥厚など)
- 嘔吐や下痢の有無
- 排尿時の様子(尿意の回数、尿失禁や夜尿症の有無、尿臭、色調)
- 発情の有無、交配歴、出産歴
◎身体検査(問診から得られた項目の獣医学的見地からの確認)
- 一般状態(意識状態、神経症状、衰弱、虚脱)
- 体温、心拍数(心音)、呼吸数
- 栄養(肥満、削痩)
- 皮下組織触診(脱水、浮腫)
- 腹部触診(肝臓・腎臓・膀胱・子宮における異常、腹水の有無、膨満感)
- 心音聴診
- 出血の有無
◎一般血液検査と血液化学検査
・一般血液検査
・血液化学検査:総蛋白質(TP)、アルブミン(Alb)、尿素窒素(BUN)、クレアチニン(Cre)、グルコース(Glu)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アルカリフォスファターゼ(ALP)、総ビリルビン(T-Bil)、γグルタミルトランスフェラーゼ(GGT)、電解質(Na,K,Cl)、無機リン(IP)、カルシウム(Ca)、総コレステロール(T-Cho)、中性脂肪(Tri)など
◎追加検査
- 甲状腺機能検査:TSH、T4、fT4
- 肝機能検査:総胆汁酸(TBA)
- 副腎機能検査:副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)刺激試験、低用量および高用量デキサメタゾン抑制試験
◎尿検査
- 尿糖、尿蛋白、ケトン体、潜血、尿比重、尿沈渣(赤血球、白血球、消費細胞、尿円柱、結晶、細菌)
- 必要により、尿培養検査
◎画像検査
- X線検査
- 超音波検査
- CT検査
- MRI検査
◎改良水制限試験
注意深い実施が望まれます。
犬の多飲、水をよく飲む病気の鑑別のポイント

問診・身体検査からの鑑別
- 問診より、食物の変更(ウエットフードからドライフードへの変更、高ナトリウム食、低蛋白食)、環境の変化(高気温、低湿度)や薬物投与歴がないか確認する。
- 問診、身体検査にて腎臓排泄以外で循環血液量が減少する消化器系疾患(下痢、嘔吐)、発熱、過換気、出血、心不全がないか診察する。
- 多尿・多飲の原因は、犬ではそのほとんどが腎不全、副腎皮質機能亢進症および糖尿病であり、猫ではほとんどの場合、腎不全、甲状腺機能亢進症および糖尿病である。これ以外の原因を考える前に、これらの疾患を併発していないかをまず診断する。
- 進行性の体重減少がみられる場合は、腎不全、糖尿病、甲状腺機能亢進症、肝機能不全、子宮蓄膿症、腎盂腎炎、高カルシウム血症(悪性腫瘍)を考慮する。
- 多食の場合は、糖尿病、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能亢進症を考慮する。
- 両側性の脱毛症およびほかの被毛・皮膚異常の場合は、副腎皮質機能亢進症およびほかの内分泌障害を考慮する。
- 尿臭のする息をする場合および尿毒症性口内炎の場合は、腎不全を考慮する。
- 嘔吐の場合は、消化器系疾患、腎不全、副腎皮質機能低下症、腎盂腎炎、肝機能不全、高カルシウム血症、低カリウム血症、糖尿病を考慮する。稀に、嘔吐は多量の水を摂取した直後に起こる。
- 2ヵ月以内に最後の発情がみられた中年齢の避妊されていない雌の場合は、子宮蓄膿症を考慮する。
- 腹部膨満の場合は、肝機能不全、副腎皮質機能亢進症、子宮蓄膿症、ネフローゼ症候群を考慮する。
- リンパ節腫大または肛門嚢腫瘤の場合は、悪性腫瘍による高カルシウム血症を考慮する。
- 触知可能な甲状腺腫瘤は、甲状腺機能亢進症を考慮する。
- 高血圧性網膜剥離の場合は、腎不全、甲状腺機能亢進症、副腎皮質機能亢進症を考慮する。
- 行動異常および神経疾患の場合は、心因性多渇、肝機能不全および下垂体障害を考慮する。
- 常に水を探し回り、どのような水でも摂取するような特に重度な多飲の場合は、原発性多飲、中枢性尿崩症、先天性腎性尿崩症を考慮する。
◎血液検査・尿検査からの鑑別
- 血清中ナトリウム濃度を測定することで、原発性多尿と原発性多飲が鑑別される(血清浸透圧測定が推奨される)。
- 高ナトリウム血症は原発性多飲を示す指標となる(ナトリウムの値は一般的に、正常域の上限または上限を超える値を示す)。
- 低ナトリウム血症は、原発性多飲を示す指標となる(ナトリウムの値は一般的に、正常域の下限または下限を下回る値を示す)。例外的に、副腎皮質機能亢進症の動物は、低ナトリウム血症と原発性多尿を示す。
- 高窒素血症の場合、多尿・多飲の原因は腎臓にあるといえるが、不十分な代償性多飲のため脱水が起きていることの指標でもある。例外的に、低BUNは、肝機能障害を示唆している。
- 肝臓酵素活性が高い値を示す場合、副腎皮質機能亢進症(特にALP値がALT値よりも高い場合)、甲状腺機能亢進症、肝機能不全、子宮蓄膿症、および糖尿病であることを示している。多飲・多尿を促進する薬物(抗痙攣薬・副腎皮質ステロイド剤など)には、肝臓酵素活性を上昇させるものもある。
- 血糖値が常に高い場合、糖尿病を示している。
- 高カリウム血症は、特に低ナトリウム血症を伴う場合は、副腎皮質機能低下症、またはカリウム保持性利尿薬の投与を示す症状である。
- 高カルシウム血症および低カリウム血症は、多尿・多飲を起こすほかの疾患を伴う場合がある。(例えば、慢性腎不全は、高カルシウム血症および低カリウム血症の両方と関連する。また、副腎皮質機能亢進症は、低カリウム血症と関連がある。)
- 高カルシウム血症による多尿は、血中イオン化カルシウムを増加させる疾患が存在するときにも起こり、上皮小体機能亢進症や悪性腫瘍を示唆する。
- 低アルブミン血症は、腎性ないし肝性の多尿・多飲を持続させる。
- 好中球増多症は、腎盂腎炎、子宮蓄膿症、副腎皮質機能亢進症および副腎皮質ステロイド剤投与を示唆する。
- 尿比重値が1.001~1.003の間にある場合には、特に原発性多飲、中枢性尿崩症、または先天性腎性尿崩症を鑑別する。尿糖では、まず糖尿病か否かを検討する。膿尿、白血球円柱および細菌尿では、腎炎、腎盂腎炎の可能性を想定する。
◎追加検査からの鑑別
- 血清中の甲状腺ホルモン(サイロキシン)濃度は中年齢の犬および高齢の猫において、甲状腺機能亢進症を判定する診断材料になる。
- TBAは後天性の肝不全および先天性門脈体循環シャントを判定する診断材料になる。
- ACTH刺激試験またはデキサメタゾン抑制試験は、初期の所見から多尿・多飲が説明されない中老齢犬の副腎皮質機能亢進症を判定する診断材料になる。ACTH刺激試験は副腎皮質機能低下症(アジソン病)も判定する診断材料になる。
- 尿の培養:慢性的な腎盂腎炎では、膿尿および細菌尿が認められないだけでは確定診断にはならないが診断の一助となる。
- リンパ節の吸引による細胞学的診断によって、リンパ腫の診断材料が得られる可能性がある。リンパ腫は、高カルシウム血症を誘発したり腎臓組織に直接浸潤したりするために多尿を引き起こす。
◎画像診断からの鑑別
腹部の検査的X線撮影および超音波検査は、
- 腎臓(原発性腎臓疾患および尿路閉塞なす)
- 肝臓(小肝症、門脈血管異常、肝臓の細胞浸潤など)
- 副腎(副腎の腫瘤、副腎皮質機能亢進症を示唆する両側性副腎肥大など)
- 子宮(子宮蓄膿症など)
に起因して多尿・多飲となる疾患を発見する一助となります。
CT検査は、脳および各臓器の腫瘍、門脈血管異常の抽出に有効です。
MRI検査は、脳の器質的変化(腫瘍、炎症、出血)を抽出するのに有効です。
◎改良水制限試験による鑑別
- 水制限には危険が伴うので一般には行わない。適切な症例か否かを十分検討する必要がある。
- 中枢性尿崩症と原発性多飲症(心因性多渇)および先天性腎性尿崩症を鑑別するために行う。この検査を実施する前に、多尿・多飲の原因がほかにないことを確認しておく。
- 顕著な多尿・多飲症状を示す場合や低張尿の動物では有効な方法である。
- この試験の原理は、飲水制限により動物を脱水させることにより、内因性のバソプレッシン(VP)の放出が刺激される状態を作り出し、この状態での腎臓の反応を観察するものである。
- 犬に適用され、猫で行うことはない。
犬の多飲、水をよく飲む病気の特徴

◎好発犬種
疾患によって異なりますが、糖尿病になりやすい犬種は以下です。
- ダックスフンド、ペキニーズ、ダルメシアン、トイ・プードル、ウェルシュ・コーギー
- 6歳以上:ダックスフンド、プードル、ポメラニアン、ボストン・テリア、ボクサー
- ミニチュア・シュナウザー、ビション・フリーゼ、スピッツ、フォックス・テリア、ミニチュア・プードル、サモエドなど
◎性差
疾患により様々である。
◎年齢
疾患により様々であるが、先天性は若齢から、後天性は加齢とともに増加します。
犬の多飲、水をよく飲む病気の高頻度の疾患

◎犬
- 慢性腎不全
- 副腎皮質機能亢進症
- 糖尿病
◎猫
- 慢性腎不全
- 甲状腺機能亢進症
- 糖尿病
犬の多飲、水をよく飲む病気のまとめ

・多尿の原因の多くは後天性腎性尿崩症であり、原疾患の鑑別が重要です。
・改良水制限試験は中枢性尿崩症、先天性腎性尿崩症、原発性多飲以外の疾患が除外されたときにのみ行うとされているが、一般に危険を伴う検査です。