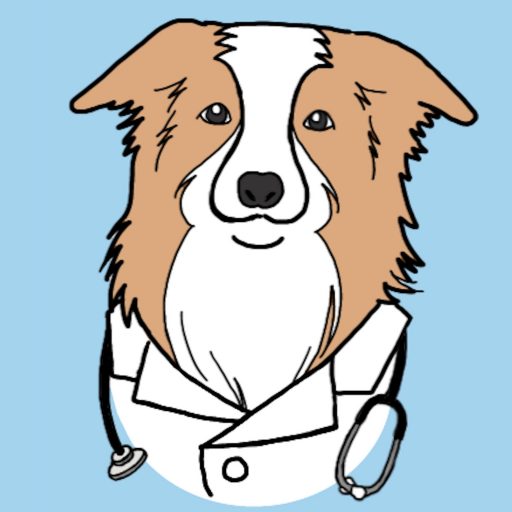最近、犬や猫が家に来て、健康診断をしたい・・・

どうやって病院を選べばいいんだろう・・・

本記事では、獣医師視点から、飼い主が選ぶべき動物病院と選ぶポイント・判断基準についてお話しします。
ネット上にも様々な情報が溢れていますが、そのほとんどが科学的根拠やエビデンス、論文の裏付けが乏しかったり、情報が古かったりします。
中には無駄に不安を煽るような内容も多く含まれます。
ネット記事の内容を鵜呑みにするのではなく、 情報のソースや科学的根拠はあるか?記事を書いている人は信用できるか?など、 その情報が正しいかどうか、信用するに値するかどうか判断することが大切です。
結論から言うと、
この記事は、飼い主が選ぶべき愛犬や愛猫の動物病院と選ぶポイント・判断基準が気になる飼い主向けです。

この記事を読めば、動物病院の選択に悩んでいる飼い主様にとって参考になる基準がわかります。
限りなく網羅的にまとめましたので、ご自宅の愛犬や愛猫のかかりつけの動物病院の選び方について詳しく知りたい飼い主は、是非ご覧ください。
内容は私がこれまで、そして現在進行形で働く中で感じたありのままの内容ですので事実であることには間違いはありません。
解釈の仕方は個人的なものであるため、それに付随する行動には責任は追えませんが動物病院選びの参考にして頂ければと思います。
病気について直接聞きたい!自分の家の子について相談したい方は下記よりご相談ください!
✔︎本記事の信憑性
この記事を書いている私は、大学病院、専門病院、一般病院での勤務経験があり、 論文発表や学会での表彰経験もあります。
今は海外で獣医の勉強をしながら、ボーダーコリー2頭と生活をしています。
臨床獣医師、研究者、犬の飼い主という3つの観点から科学的根拠に基づく正しい情報を発信中!
記事の信頼性担保につながりますので、じっくりご覧いただけますと幸いですm(_ _)m
» 参考:管理人の獣医師のプロフィール【出身大学〜現在、受賞歴など】や詳しい実績はこちら!
✔︎本記事の内容
獣医師視点からの、飼い主が選ぶべき動物病院と選ぶポイント・判断基準
この記事の目次
どんな時に動物病院に行くか

家に犬や猫がいる家庭の場合は、動物病院を受診するタイミングは下記の2通りだと思います。
- まず、 いぬ・ねこを飼い始める
↓ - 暮らし始める
↓ - 予防接種、避妊/去勢 どうすればいいの?
↓ - 病院へ行く
もしくは、
- 少し歳のいったいぬ・ねこを飼い始める
↓ - 暮らし始める
↓ - なんか体調悪そう??
↓ - 病院へ行く
今行っている病院本当に大丈夫ですか?


そんな時に、その病院 どのように選んでいますか?
- とりあえず、一番近いところにしよう!
- ネットで検索してみて、なんかHPがいい感じ!行ってみよう。
どうぶつ病院選びではまずそんなことを考えがちです。
行ってみたら当たりだった。
うちの子にもあっていそう! というならいいのですが、それだけで選んで良いのでしょうか?
人の病院のように動物病院ではすべての機材が洗練されているわけでもなく、獣医のレベルによってもされる治療内容が異なることなどよくあることなのです。
病気なら尚更ですが、ワクチンや予防といった最低限の基本的な医療に関しても、常に勉強をして知識をアップデートしていなければなりません。
例えば、ワクチンは
昔は2−3ヶ月齢までに2、3回。そして毎年ワクチン摂取
今は、生後半年まで5−6回。その後は2−3年に一回
になっていますが、いまだに毎年注射を指摘されている飼い主様が多いのではないでしょうか?
命がかかっている現場で、漫然と昔と同じことをしていると非常に危険です。
健康な時は、大事になることはあまりないですが、いざ病気になってから病院を探しては遅いのです。
受診する動物病院によって変わること、違い

以下に動物病院によって異なるものを挙げてみます。
- 医療レベル
- 獣医師の経験値
- 機材、設備の充実度
- 料金設定
- 待ち時間
- 飼い主、動物との相性
などが挙げられますね。
どの内容も大事な構成要素ではありますが、一番重要視するのはその病院の医療レベルではないでしょうか。
医療レベルと一言にいっても ・自分の望む治療をしてくれること ・最先端の最善の治療をしてくれること ・費用の少ない、待ち時間の少ないスムーズな診療をしてくれること など、望むものは人ぞれぞれだと思います。
ただ実際には自分の望むものでかつ費用も抑え、待ち時間の少ない、最先端の治療をして欲しいというのが本音でしょう。
しかし それは獣医師、動物病院側の立場から言えば全てを同時に叶えるのはおそらくかなり難しいです。
できるとしても、動物病院と飼い主様とでしっかりとした信頼関係を築いて初めて叶えられるものだと感じます。
そんな動物医療の現場から病院選びの『コツ』を。あくまで私の経験をもとにお伝えします。
まず大前提として動物病院には(獣医師だから敢えて言いますが)ヤブと言われるような治療をする病院があります。
そうです。それは間違いなく、存在します。(どこの業界も同じですよね)
しかし、命が関わっているので、ヤブも問題ですし、時代遅れの治療も以前は正しくても問題です。
最新の治療で治せるものを、以前の知識で治せない認識、知識でいると誤った結果を生んでしまいます。
もちろん、全ての治療の選択肢を提示された上で、飼い主様がそのメリット・デメリットをそれぞれ理解した上で、選んでいただければ、最新の治療をしなくてもいいのです。

金額、距離、動物の負担などを考慮して、後悔しない治療方法を選んで欲しいのです。
そんな病院に行って診てもらってしまったらそれは何よりそのペット達がそして飼い主様が不幸になるだけではないでしょうか。
このように書きましたが、多くの病院はいい先生方で、日々動物の治療のために勉強をされており、可能な限りの最高の治療をすべく努力されていることも私は知っています。
しかし、そんないい先生、いい病院に巡り合えるかどうかが運で決まる以外に方法はないのでしょうか?
病院のホームページを見ても、いいことしか書いてありません。
そこで、あくまで悪い病院を避ける方法をお伝えします。

愛猫や愛犬のわずかな変化に気づくことができる、守ることができるのは飼い主様だけです!
病気になった時も、獣医師がしっかり説明をして、飼い主様が正しい知識を理解をして、ペットを含め、3人がともに協力しないといい結果は得られません。
獣医師任せにしては絶対にいい結果は得られません。
獣医師は飼い主が、早く動物を連れてきてくれないと治せませんし、犬や猫は飼い主頼りです。
飼い主様が、治療を望まなければ治療しませんし、希望されれば治療します。

私たち獣医はあくまで飼い主様の希望を、医学的な面から援助する、手助けするだけで、この仕事をしていると、医療の限界、無力を痛感します。
治せないものは治せません。
治せるものを、知識、技術を使って治しているだけなのです。
常に一緒にいるのは飼い主様だからこそ、飼い主様が状態の変化を一番に見つけることができるのです。
安易な経過観察も危険です。
もっと本音を言うと、すべての動物病院の医療レベルが上がっていくことがこれからの動物医療の発展につながり、それは人と動物の社会が幸せになることだと言えると私は考えています。
ですので、飼い主様の目が肥えることで自然と動物医療のレベルも向上するとも言えるのではないでしょうか。

病院のサイトやホームページ、さらに実際に受診してみたときから得られる、その病院の本当の姿を見極められる様にしましょう。
いい病院に巡り合う、選ぶポイント

では、それぞれの内容についてみていきましょう!
ここまで書いたのは私の理想ですが、動物病院選ぶ上でこれからの情報を参考にして頂ければ幸いです。
先程あげた動物病院によって異なるものとして ・医療レベル ・獣医師の経験値 ・施設、設備の充実度 ・料金設定 ・待ち時間 ・飼い主、動物との相性 がありました。
医療レベル
では、まず 医療レベルとは なんでしょう??
これは「ある一定の水準、例えばガイドラインのようなものがあるとしてその水準を満たす治療をどれだけ行えているかどうか」 ということでしょうか。
それが獣医療ではまだまだ不完全なのです。
言い換えると、医療レベルとは 「ある一定水準を満たし、超えるだけの治療を行えるかどうか」 ということですね。
これが論文、報告、科学的根拠です。
新しい、正しい治療は、多くの動物の犠牲の上にわかってきた僅かな事を基本的に行われます。
それが記されているのが教科書、論文です。
決して個人の先生による、わずかな経験に基づいたオリジナルの方法ではありません。
残念ながら、そう言った治療をしている病院があるからこそ、動物病院によって異なるもの という上記の内容が当てはまるのです。
例えば、代表的なものに混合ワクチンがあります。
混合ワクチンは近年まで、日本では、多くの動物病院、ペットショップなどで、
生後2、3ヶ月齢までに一月毎に2、3回打って、その後は毎年という説明があったと思います。
そのため、ほとんどのペットホテルやドッグランでもそれを採用してきました。
しかし、日本以外では以前からワクチネーションプログラムが変化しており、生後半年まで毎月合計6回程度注射して、
その後は2−3年に一回となっております。
近年、その流れがやっと日本に入ってきました。
にもかかわらず、依然として過去と同じ治療を、同じ様にやっている病院はあります。
獣医師解説!本当に必要な犬の混合ワクチン間隔 論文、エビデンスあり!
犬にワクチン摂取って毎年必要なの?病院、ペットショップ、トリミング、ペットホテルでは毎年ワクチン摂取が必要と言われた。毎年のワクチン摂取は日本の獣医師が儲ける為?実は、ワクチンは毎年必要ではない?!。この記事では、犬の混合ワクチンの摂取間隔をアカデミックな面から、よくある疑問をまとめました。
獣医師解説!本当に必要な猫の混合ワクチン間隔 論文、エビデンスあり!
猫にワクチン摂取って毎年必要なの?病院、ペットショップ、トリミング、ペットホテルでは毎年ワクチン摂取が必要と言われた。毎年のワクチン摂取は日本の獣医師が儲ける為?実は、ワクチンは毎年必要ではない?!。この記事では、猫の混合ワクチンの摂取間隔をアカデミックな面から、よくある疑問をまとめました。
ですので、そういった病院には注意が必要で、過去には治せなかった病気でも、現在治せるものはたくさんありますが
そこの獣医の知識がそこでストップして、新しい知識を取り入れておらず勉強していないと、
その先生の限界が医療レベルの上限となります。
獣医師の経験値
上記の論文、教科書に基づいた治療ができるかは当然です。
しかし、病気がどの様な病気か、疾患名かわからなければ治療のしようがありません。
病気の子がきた場合、どう言った検査をすれば診断ができるのか。
その知識も重要ですし、経験も必要です。
逆に言えば診断ができれば、あとは上述の様に治療方法は決まっているため、それに沿って治療をするだけです。
つまりそれは、その獣医師が治療した経験があるかどうか ということになります。
想像してもらえるとわかるかと思いますが、自分が治療したことがない病気は治せません。
参考書を見ながら見様見真似で治療はできますが、そんな治療はされたくないですね。
これはもうその通り、検査方法も、診断方法も、治し方も分からないので当たり前と言えば当たり前です。
ですが、動物病院に勤めていれば治したことのない病気には必ず出会うもの。
筆者の経験では獣医師になって5年以上、ある程度の診療をこなしていれば大体の病気は治療した経験があると思っています。
ただし、手術などはさらなる経験も必要なので、若手獣医師の場合は上級獣医師と共に手術を行いあたかも自分が手術をしたかのように話すこともあります。(これは実話です)
獣医師も新人もいれば、中堅クラスもいるし、なんでもこなせるレベルの人までいろいろなレベルがあります。
さらに同じ5年目の獣医師でも、1次病院で去勢や避妊手術、ワクチンにメインを置いてきたか、2次病院や大学病院で重症な子を経験してきたかにもよって変わります。
それは恐らく人の医者もそうでしょうし、その獣医師のレベルで医療レベルが決まってしまうこともザラだと言えます。
しかし、その治療を行うのはその担当した獣医師だけではないのです!
これは手術の時も同じです!
同じ病院の上級獣医師と共に相談しながら検査、診断、治療を進めていくのです。
それはつまりその獣医師のレベルだけではなく、共に働く獣医師のレベルによっても治療レベルが変わってくることを意味しています。
つまり 医療レベル = 担当獣医師のレベル + 同じ病院の上級獣医師のレベル ということになります。
ですので、必然的に個人でやっている小さな病院では 病院の医療レベル = その院長先生の実力 が上限となっています。
通常はある程度様々な症例経験を積んだ上で開業するため、院長であればある程度できることは前提ではあります。
ただ、私の知る限りではそのレベルによってはかなりお粗末なケースもあるので注意が必要です。
また、綺麗で施設の整った病院を若い獣医師が一人で運営しているからといって、その病院の医療レベルが高いとは必ずしも限りません。
病院のレベルが高いのではなく、施設、設備を揃えるだけのお金が用意できる環境にある(親、親戚に援助してもらうなど)だけの場合もありますので注意が必要です。
院長に見て欲しい。
それもわかります。
しかし、獣医療のことを考えると若い先生が育たないと、結局医療は衰退していきます。
自分の子だけは院長に見て欲しい、そう言った飼い主が増えれば増えるほど若い獣医師は成長する機会を失います。
大学病院は基本的には教育を主としており、報告や論文に基づいた検査、治療を実施しています。
実際に海外の大学病院は、日本よりも教育に力を入れており、研修医が診察を行います。
飼い主がその理念を理解できない場合は、受診を断る場合もあるそうです。
いい治療や獣医が育つためには、飼い主様にも協力していただかないと上達しません。
では、どの様な経験をしている獣医師ならいいのか?
一番確実なのは、大学病院を経験していることです。
上述の通り、大学病院は教育病院であり、かつEBM(Evidence based medicine):論文、教科書を基礎に治療を行います。
病院のホームページの、院長紹介欄の経歴をご覧ください。
決して、大学病院を経験していないと、ダメというわけではありません。
あくまで指標の一つです。
施設、設備の充実度
病院の、サイト、ホームページには設備のページで、様々な設備がPRされていると思います。
そのページを見ている飼い主様は少ないんではないでしょうか?
おそらく、その病院にどんな設備があるかまで興味を持って調べている飼い主は少ないと思います。
また、この設備があるからこの病院に行こうということもあまりないと思われます。
飼い主様と検査機器が関係する場合は、動物病院に行った時に最もされる検査、それは血液検査が一番多いと思います。
血液検査は、数値で異常が出てきますので、多くの病院で差はありません。
むしろ必要な項目がされているかどうかが重要です。(いろんな病気が疑えるかどうか)
最悪、その病院に血液検査の機械・設備がなくても、
外注検査と言って、採血した血を外の検査センターに送ることで、割高になり、時間はかかりますが、検査は可能です。
ですので、血液検査の機会に、いいものを使ってもあまり変化はありませんし、数値は客観的なものです。
どこで検査を行ってもほとんど同じです。
しかし、超音波検査やレントゲン検査はどうでしょうか?
血液検査とは異なり、数値で出ない、超音波検査とレントゲン検査は、獣医師の養われた目が必要になります。
上記の検査は、画像として出てくるので、経験のある獣医師には見える異常も、経験が浅いと見逃す可能性もあります。
いい超音波、レントゲン装置は、非常に高価です。
安価な機器を使ってしまうと、画質が悪くなり、さらに見逃しが増えてしまいます。
ですので、超音波装置、レントゲン装置にはコストをかけている病院がお勧めです。
しかし、非常に高価な機械を購入しても、その検査費用をいきなり飼い主に負担させるわけにはいきません。
そこはワクチンや、薬などで少しづつ回収しないといけないのです。
さらなる精密検査として、骨髄検査、関節鏡検査、CT検査、MRI検査などがありますが、これらの検査は専門病院にお任せした方がいいので、紹介してもらうことがほとんどですので、あまり気にされなくても大丈夫です。
もちろん今行っている病院にある場合は、技術的に非常に優れた病院で、勉強熱心な獣医師がいる証拠です。
料金設定
しかし、一般的に手術は費用が高いです。
手術の時は、麻酔薬、手術器具、ガウン、ドレープ、鎮痛剤など非常にコストがかかります。
時間当たりの単価だけで考えると、手術よりも、ワクチンの方が儲かります。
それでも手術をするのは、手術が一番いい治療法の病気の時に、飼い主様が望む時で、緊急時が多いため、獣医師も安くしてあげたいのです。
そのためには、他のところの値段を上げざるを得ません。
慈善事業ではありませんので、安くしている手術費用を賄うためにも、薬やワクチンで多めにいただいているわけです。
つまり、飼い主様が、他の飼い主のペットを負担しているということです。
手術は緊急性を要するのに、お金を請求するなんて、と思う方もいるでしょう。
病院によっては、分割や、あとでいいですよというところもあります。
結局支払う飼い主は多くないです。
- そのまま音信不通になる飼い主
- 金の亡者と騒ぎ立てる飼い主
そうやって毎年何百万も未収金が出て、潰れた病院を知っています。
弁護士まで立てて、回収している病院もあります。
人情味溢れた病院が損をする、そんな状況になっているからこそ内金を、たとえ緊急時であっても請求する病院は多いです。
潰れると、しっかりお金を払った飼い主、そこの病院が近くてそこが救いだった飼い主のペットにも迷惑をかけてしまいます。
もちろんぼったくり獣医もいます。
ですが、安いから=いい病院ではないという事をご理解ください。
手術費用が安い時は、痛み止めを使っていない、抗生剤を使わない、器具を清潔に滅菌していない、などでコストを抑えています。
術後、痛みで犬や猫が、泣き叫んでのたうちまわっているのをご存知でしょうか?
ぼったくり以外で、費用を安くすると、飼い主の負担は減る一方で、陰でペットの負担が増えています。
安さを選ぶと、帰ってから痛みで、結局泣き叫んで夜間病院に行くハメになります。
ただし、安いに越したことはありませんし、ぼったくりの獣医もいますので、基準となる様な目安は下記に記載します。
- 去勢手術:2−3万
- 避妊手術:4−5万
- 腫瘍などの軟部外科手術:30−40万
- 骨折や脱臼、ヘルニアなどの神経整形外科手術:50−60万
待ち時間
人気だからと言って、飼い主様全員に合うかは、また違う問題ですが、飼い主が多いのには理由があります。
有名な病院は、いまだにネットやgoogleの口コミよりも、飼い主同士の口コミで広まることが多いです。
飼い主同士では、医療面で正しいかどうかよりも、先生の人柄や治ったかどうか、同じ症状が出ているなどで判断していると思います。
ですので、医学的に正しくなくても、人当たりなど、飼い主に寄り添う病院だということは判断できます。
しかし、コロナウイルスのこともあり、人が多い待合室に抵抗のある方、待つのが苦手なワンちゃんや猫ちゃんは、その病院の中で、診察数が少ない先生や、電話で順番が近くなったら呼んでもらうのがいいです。
順番が近くなったら呼んでもらうのはそのままですが、
上記の理由でその病院の治療のレベル=院長です。
つまり若い先生であっても、その先生の手に負えなければ院長に助けを求めるはずです。
飼い主の中には、無意味な「院長信仰」の方がいます。
でもそのせいで、ワクチンや健康診断・相談など、院長以外でも対応できる犬や猫が院長に集中するために、どんどん待ち時間が長くなります。
思い切って、「どの先生でもいいです。」と受付で言ってみると早く診察してもらえるかもしれません。
しかも、若い獣医師が担当すると、若い獣医師の方が勉強熱心ですし、獣医師にとっても勉強になり、結果獣医療の向上にもなります。
飼い主、動物との相性
こればっかりは、健康な時にいろんな病院に行ってみるしかありません。
googleの口コミも気にしないでください。
- たとえば、猫と犬で待合室の階や場所が異なっていたり、待合室が広かったりなどです。
- 階段がなかったり、粗相をした時にすぐ片付けてくれるスタッフがいることも重要です。
飼い主様自身のペットのことです。
健康な時に、いろんな病院に行ってみて雰囲気を自身で受診して判断してください。
ただし、どんなに気性が荒い動物でも、時には鎮静剤を使うことで診察は可能です。
鎮静剤は、麻酔ほど強力ではないのですが、抵抗がある飼い主様も多いです。
ですが、嫌がる動物を起きたまま、検査することは、非常にストレスです。
鎮静でぼんやりしている間に、終わらせて、起きたら全ての治療を終えていることは、飼い主にとっても、動物にとっても有用です。
ですので、単純に、あそこの病院はすぐ麻酔や鎮静をかけるからダメだとか、
あそこの病院は無麻酔でやってくれるから安心だ
というわけではありません。
健康診断をしているか
飼い主様の中には、健康診断をして欲しいという方はいるのではないでしょうか?
しかし、動物病院は結構忙しいので、健康診断セットをしているところはあまりありません。
血液検査、超音波検査、レントゲン検査、尿検査をセットで安くしているところは多いです。
報告上は7歳までは1年に1回、7歳以上は1年に2回と言われております。
通常の業務の中で、上記の様な健康診断を実施しているということは、スタッフの人数、設備に余裕がないとできません。
猫の病院の指標の一つ
「Cat Friendly Clinic (CFC)」に認定されている動物病院を選ぶと良いかも。
CFCに認定された動物病院は、猫に関する専門性の高い知識で、質の高い猫医療を提供できる「猫にやさしい動物病院」と言えるでしょう。
「CFC(Cat Friendly Clinic)」とは、猫にやさしい動物病院の“道しるべ”としてisfmによって確立された国際基準の規格で、世界的に普及しています。
CFCに認定された動物病院とは、猫専任従事者を設けることでより猫の専門性の高い知識と質の高い猫医療を
提供することを猫のご家族に約束し、猫にやさしい動物病院の“道しるべ”となります。
CFC取得には、国際基準を満たす必要があります。
動物病院内での設備・機器などに関して満たすべき基準があります。
JSFM Japanese Society of Feline Medicine (JSFM、ねこ医学会)
JSFMはisfmの公式な日本のパートナーとして認定されています
説明、インフォームドコンセントについて
最後に、ワクチンや医療サービス、治療の説明に関してです。
- 例えばワクチンの間隔は上記の通り、変化しつつあります。
- また、ワクチンによるアレルギーは20−30万頭に1頭と言われており、重度になると呼吸が止まる可能性もあります。
- ワクチンによるアレルギーの場合は、嘔吐や、顔が赤くなる腫れる、ぐったりするなどが症状として出てきます。
- たかがワクチンであっても、そう言ったリスクの説明があるかどうか、注射の際に体温や聴診をしているかどうかも重要です。
- また、病気の治療も同様です。
麻酔のリスクや、検査をするかどうかも重要です。
- つまり、積極的な検査、治療が全ての飼い主、犬や猫にとってベストかどうかは別問題です。
- それぞれの家庭の状況や費用、治療方針、考え方、意向に沿ったオーダーメイドの治療法こそがベストです。
- それがたとえ検査、治療をしないという方針でもいいのです。
- それであれば、例えば痛い場合でも、痛みの原因の治療ではなく、痛み止めの薬という手段もあるからです。
- 医学的に積極的な治療、消極的な治療、ベストな治療、ベターな治療を組み合わせる、説明してくれる獣医師がいいと思います。
- 例えば、95%の患者が治る病気だったとしても、5%に自身が当てはまれば、その方にとっては100%になります。
- 病気の治療方法も様々です。
- 外科治療、内科治療、放射線、免疫治療などです。
- それぞれのリスク、メリット、デメリット、費用、治る確率、予後などをしっかり説明してくれる要因が良い病院です。
獣医の仕事は、何がなんでも、飼い主からペットを奪っても、治療をする仕事ではありません。
あくまでも飼い主の以降に沿った医療サービスを、その知識、技術を持ってお応えすることが仕事です。
つまり技術、知識を元に、飼い主の意向に沿ったサービスを提供する、究極のサービス業です。
わんちゃんや猫ちゃんは喋れないからこそ、今まで一緒に生活してきた、飼い主が決めた治療こそが、積極的できなくても
正解だと思います。
積極的な治療、対症療法、自宅で看取る、いずれも十分考えた結論であれば、それをフォローするのが獣医師です。
たとえ自宅で看取る場合でも、最後に苦しいや痛い、しんどいは避けたいので、薬を渡すこともできます。
それぞれ意向に沿った、違う目的の薬があるので、いかようにも調整できるのです。
血液検査で異常がないからと言って、病気がわからないですと説明された飼い主(病気によっては血液検査で異常が現れないことも多々あります。)
- 血液検査で異常がない=健康ではなく
- 血液検査で異常がない=血液検査に異常が現れない病気
なので超音波検査やレントゲン検査をしましょう となるわけです。
他にもウンチの検査、特に若い子ですることが多いですが、おおよそ感度が70%と言われております。
- つまり3頭に1頭くらい見逃します。
- ですので2−3回間隔を開けて治療することが多いのですが、その事を説明せず、1回の検査で寄生虫はいないと信じている飼い主。
手術や麻酔、治療の説明について
また、全ての病気、治療方法、その予後、寿命については、報告、データがあります。
データはあくまで今までの経験による結果です。
手術や治療に悩む飼い主へ「成績」「成功率」についてお話しする時は、例えば以下のように伝える病院がいい病院だと思います。
「この子にとって手術は未来のことです。ですから過去のデータがどうであれ、この子にとって手術後元気になるかどうかは五分五分です。ただ、我々のチームは、手術をすれば9割の子を元気にする実績をもっています」
「治療した時のメリット、デメリットはこういったものがあって、費用はこれ位です。治療しなかった時のメリット、デメリットはこういったもので、これ位生きてくれる可能性がある。今後こういうことがあって、徐々に悪化が考えられる。」
「決して積極的な治療がベストとは限らず、そのペットや飼い主にとってのベストな治療法、ベターな治療法を考えて行き、オーダーメイドな治療法を探しましょう。」
この伝え方が100%正解ではないとは思います。
しかしどんな手術であれ、去勢や避妊手術であれ、どんなアクシデントがあるかは手術をしてみなければわからないというのが本当のところです。
ですので、下記のどれに当てはまるかを、それぞれメリット、デメリット、予後、寿命を総合的に考えて相談してくれる先生、選択肢を与える先生がいい先生だと考えます。
- 手術(治療)できるからする
- 手術(治療)できるけどしない
- 手術(治療)できない
- 手術(治療)したくない
そして、その中でも更に、自分の場合を伝えてくれる先生がいい先生だと私は思っていますし、私はそうしています。
つまり、専門的なことを並べられて、「はい。選んでください」と言われても困りますよね?
結局、この子にとってはどれがいいの?ってなりませんか?
そんな時に、一つの参考として、いち獣医師の僅かな経験上ではありますが、
「もし私の犬が、飼い主様の犬と同じ状況だったら、こういった治療方法を選びます。」
この発言は多くの飼い主様の背中を押してくれる言葉だと私は信じています。
つまり、近年はネットで調べれば、その信頼性や正しいことかどうかは置いておいて、犬や猫の病気の情報はいくらでも出てきます。
しかし、情報の取捨選択の基準がない中で、ただネットの知識だけで救うことはできないので、
実際に状態を見ている獣医師と共に、その子その子に合った治療方法を選ばなければなりません。
そのためには、獣医師が「これしかないです!」
ではなくて、獣医師が「こういう治療方法と、こういう治療方法があって、、、どうしますか? 参考までに私の子であればこうします。その根拠は、、、」
という相談がいいと思いませんか?
高齢のペットは若いペットに比べて、手術の危険性はもちろん上がります。
確かに手術をするなら若い方がいいと私も思います。
ただ、高齢だからといって手術しない・・・これはどうかと思いますね。
特に高齢と言う理由だけでは「出来ない」ということはないのです。
獣医に、麻酔がかけることができないと言われたときには
やりたくない、自信がない、設備がない、面倒だ、人が足りない、
などの理由が多いです。
しっかりとした設備、人の数、そして経験、信念を持った病院であれば、老齢のペットであろうとしっかりと検査をして、それに合格すれば手術を行います。
現在は麻酔も大変良いものが揃っていますし技術が伴っていれば、麻酔のリスクは0.01%と言われています。
代表的な、麻酔リスクは、血圧低下、心拍低下、呼吸不全、アレルギーなどです。
いくら老齢だからといって、寿命が延びるのであれば飼い主は手術を希望することが多いです。
それを勘違いして、「わざわざもう手術することはないでしょう。年ですし。」と勝手な考えで手術の話すら出さない獣医は実際にいるのです。
「老齢ですし、手術はやめた方がいいですね。」と言われたら、なんでダメなのか、他の病院でも同じ事を言われるか、検査はしっかりやってみたのか、確認するといいです。
もっともっとあなたのペットは生きられるかも知れませんよ。
あなたのかかりつけの先生に質問できますか?
さらに、飼い主が質問しやすい環境や、質問しても嫌な顔をしないというものも重要です。
当然だと思われる方もいるでしょう。
しかし、いまだに
- 質問すると嫌な顔される
- 怒られる
- 質問できる雰囲気ではなくて高圧的
- 飼い主の話を聞かない
という獣医師はいますし、それで困ってる飼い主がいることも事実です。
もちろん獣医師からは医学的な言葉も出ます。
1回で完全に理解できなくても、治療には飼い主様の理解が必要なので、獣医師の立場としては、飼い主様にしっかり治療の目的や治療内容を理解していただきたいのです。
だからこそ、不明な点は聞いて欲しいですし、私は説明の後に、「ご不明な点はございますか?」と必ず聞く様にしています。
その一環として、良い病院のサインとして、薬の名前を袋などに書いてあることがあげられます。
上記の理由と被りますが、飼い主が無知なのを良いことに、また、調べられても困らない様に薬の名前を言わずに、また、薬の名前を書かずに処方している病院があります。
人の薬局、処方箋ではあり得ないですよね?
かならず添付文章がついています。
飼い主自身で、ネットで治療法を調べられて、違う薬が出た場合に言い訳できないからです。
まとめ
私の独断と偏見、経験によって、いい病院の判断基準をまとめましたがいかがだったでしょうか?
どこの業界もそうですが、ホームページや上部のサイトではいいことしか言いませんし、あくどいところがあるのも事実です。
内部を公開する人はいませんし、大事な家族を任せるからこそ心配にもなりますし、不安にもなりやすく、疑心暗鬼になりますよね。
さらにネットで情報を見ると、自分が見たいところしか目に入らなくなるので、ますます疑心暗鬼になります。
買い物で騙されただけであれば、お金を無駄にしただけですみますが、命がかかっている治療で同様のことがあると、取り返しがつきません。
医療のことはわからないと、獣医に丸投げして、治療が上手くいかなかったら全責任を押し付けるのではなく、自身で防衛して、大事な家族を守る必要があります。
病院を探すのも大変ですが、犬や猫で心配事があった時に、ネットで検索することはもっと大変で、慎重さが重要です。
情報を上手く使い、踊らされないことが重要です。

飼い主様がたどりついて、調べたその記事やブログは本当に信頼できますか?誰が書いているかわかりますか?
ネット上には様々な情報が溢れていますが、そのほとんどが科学的根拠やエビデンス、論文の裏付けが乏しかったり、情報が古かったりします。
中には無駄に不安を煽るような内容も多く含まれます。
ネット記事の内容を鵜呑みにするのではなく、
情報のソースや科学的根拠はあるか?
記事を書いている人は信用できるか?など、
その情報が正しいかどうか、信用するに値するかどうか判断することが大切です。
獣医師解説!現役臨床獣医師がおすすめする、いい病院の選び方!かかりつけ動物病院の決め方
最近、犬や猫が家に来て、健康診断をしたい・・・どうやって病院を選べばいいんだろう・・・本記事では、獣医師視点から、飼い主が選ぶべき動物病院と選ぶポイント・判断基準についてお...
病気について直接聞きたい!自分の家の子について相談したい方は下記よりご相談ください!
✔︎本記事の信憑性
この記事を書いている私は、大学病院、専門病院、一般病院での勤務経験があり、 論文発表や学会での表彰経験もあります。
今は海外で獣医の勉強をしながら、ボーダーコリー2頭と生活をしています。
臨床獣医師、研究者、犬の飼い主という3つの観点から科学的根拠に基づく正しい情報を発信中!
記事の信頼性担保につながりますので、じっくりご覧いただけますと幸いですm(_ _)m
こんなことについて知りたい!これについてまとめて欲しい!というのがあれば下記からお願いします!